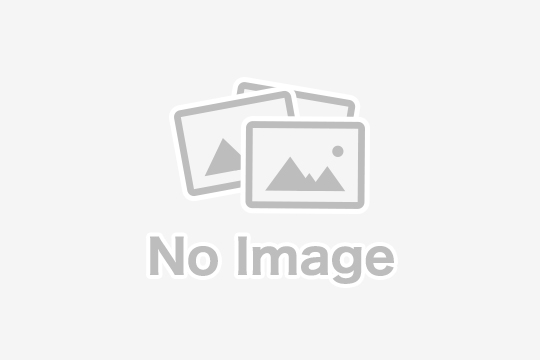阿部幸大による『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』は、その名の通り従来のアカデミック・ライティングに関する書籍とは一線を画す、革新的なアプローチを提供する書籍である。本書の目的は、初学者が独学で論文を書けるようになること、そして中級者・上級者がより効果的に論文を執筆できるようになることである。従来のアカデミック・ライティング書籍が技術的な面に重点を置くのに対し、本書は人文学における論文執筆の本質的な部分を解明し、論文の意義や価値についても深く掘り下げている点が特徴的である。
第1章 アーギュメントをつくる
本書の冒頭では、論文の核となる「アーギュメント(主張)」の重要性が強調される。論文は単なる情報の羅列ではなく、明確な主張を展開し、それを論証するものでなければならない。本章では、アーギュメントとは何か、どのように形成するのかが詳細に解説されている。
アーギュメントの基本的な要件として、「論証が必要な主張であること」「反論可能であること」が挙げられる。例として、アンパンマンの物語をジェンダーの視点から分析する際に、単なる観察ではなく、「『アンパンマン』の物語は男性中心的であり、女性キャラクターが周縁化されている」という主張を立てることで、論証が可能なアーギュメントへと発展させる過程が示される。
また、他動詞モデル(「AがBをVする」という形でアーギュメントを構成する)を活用することで、論証の強度を高める手法が紹介されている。このアプローチは、特に初学者にとって有効であり、論文の骨格を明確にする助けとなる。
本書が特に優れているのは、アーギュメントを鍛えるための具体的な演習を豊富に提供している点である。たとえば、特定の文章を他動詞モデルに変換することで、論証の強度を向上させる練習が紹介されている。こうした演習を通じて、読者は論文執筆における思考の流れを自然に身につけることができる。
さらに、本章では論文の「問い」の重要性についても言及される。アカデミックな議論では、明確な問いを立てることが論証の基礎となるため、単なる情報の整理ではなく、研究の意義を理解しながら問いを設定する方法が詳細に説明されている。
また、学問領域によるアーギュメントの違いにも焦点が当てられている。例えば、社会科学においてはデータを用いた論証が求められる一方で、人文学では概念の精緻化や文献解釈が重視される。本書では、これらの違いを理解し、各領域に応じた論証の技法を身につけることができる。
さらに、著者は論文の構造を設計する際のポイントとして「フレームワーク思考」を提案する。論証の流れを明確にし、各セクションが適切につながるように設計することで、論文全体の一貫性を確保できる。この手法は、特に博士論文や学術論文を執筆する際に有効であり、論理の飛躍を避けるための実践的なアプローチとして紹介されている。
第2章 アカデミックな価値をつくる
次に、論文の価値を決定する要因について議論される。論文において「面白さ」は主観的なものであり、評価の基準としては不十分である。そのため、本章ではアカデミックな価値をどのように生み出し、評価するかが論じられる。
著者は、アカデミックな価値の基準として「先行研究との関係性」を重視する。単なるオリジナリティではなく、既存の研究を踏まえたうえで新たな視点を提示することが求められる。例として、日本の論文執筆指南書に見られる「問いを設定することが論文の要件である」という通説に対し、本書は「論文はアーギュメントを論証するものであり、問いの有無は本質的でない」と反論している。このように、既存の枠組みを見直し、新たな論点を提示することがアカデミックな価値を生む方法であることが示される。
本章ではまた、査読のプロセスについても詳しく解説されている。学術論文がどのように評価され、どのような要素が重要視されるのかについて、具体的な事例を交えて説明される。査読者がどのような観点で論文を評価するのかを理解することで、読者はより適切に論文の質を向上させることができる。
特に、論文の影響力を高めるための戦略についても論じられており、読者は単に論文を執筆するだけでなく、それをどのように読者に届けるかについても学ぶことができる。
また、国際的な視点から見たアカデミック・ライティングの特性や、日本と欧米の論文スタイルの違いについても言及されている。これにより、英語論文を執筆する際の注意点や、国際学術誌に投稿する際のポイントを理解することができる。
総評
『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』は、単なるライティング技法の指南書にとどまらず、アカデミックな議論にどのように貢献するかを問い直す内容となっている。特に、人文学における論文執筆の本質に迫る点で、他の類書とは一線を画す。
また、本書は日本の学術界の特性にも触れており、研究者としてのキャリア形成や、学術的なネットワークの重要性についても示唆を与える内容となっている。
総じて、本書は人文学におけるアカデミック・ライティングの新たなスタンダードを確立する可能性を秘めた一冊であり、学生から研究者まで幅広い層にとって有益な指南書である。
※ この記事はchatGPTを利用して書かれています。不正確な情報が含まれる可能性にご注意ください。