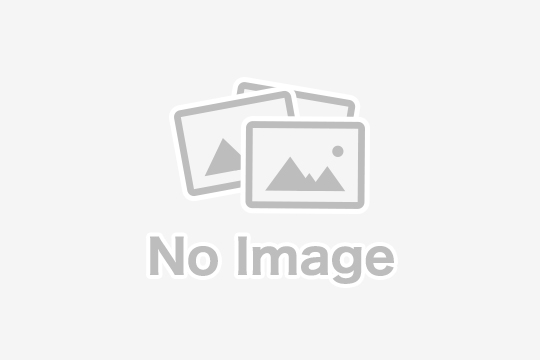本書『多元世界に向けたデザイン』は、コロンビア出身の人類学者アルトゥーロ・エスコバルが、デザインを通じて現代社会の変革を試みる野心的な試みを提示する書籍である。エスコバルは、伝統的なデザインが近代の存在論的枠組みに囚われていることを批判し、新たなデザインの実践を提唱する。
序章:デザインの存在論的転回
本書の序論では、デザインが単なる物の設計や都市計画にとどまらず、我々がどのような世界を作り上げるのかという根本的な問題に関わることを指摘している。エスコバルは、近代のデザインが「モダニティ」の枠組みに基づき、二元論的な思考(主客の分離、人間と自然の対立など)に囚われていると批判する。そして、代替的なデザインのあり方として「存在論的デザイン(ontological design)」を提案する。この概念は、デザインが単なる道具的な役割を超え、文化的・社会的実践そのものであることを示唆している。
この序章では、エスコバルの提唱するデザインの変革がなぜ必要なのかを歴史的背景から説明する。従来のデザイン理論は、産業革命以降の技術主導の発展と密接に関わり、機能性と効率性を追求する一方で、社会的・環境的な影響を軽視してきた。デザインがどのようにして社会構造の一部となり、どのようにして権力を維持する手段になったのかを振り返りながら、新たなパラダイムへの移行が求められていることを説いている。
第一部:現実世界のためのデザイン
第一部では、近代デザインがどのように世界を構築してきたかを詳細に分析する。特に、開発や資本主義と結びついたデザインの歴史的展開を示し、それが環境破壊や社会的不平等をもたらしていることを論じる。
近代デザインは、特定の価値観や政治的立場を反映しており、その発展は単に技術的な進歩ではなく、社会制度や経済構造の影響を受けている。例えば、都市計画の歴史を振り返ると、西洋の近代都市デザインは、産業革命とともに発展し、効率性と経済成長を優先する形で設計されてきた。その結果、多くの都市は、貧富の格差が拡大し、都市の中心部には裕福な層が住み、周縁部には労働者階級や社会的に不利な立場にある人々が押しやられる形になった。
エスコバルは、こうした都市の構造が決して自然なものではなく、デザインの選択によって意図的に作られてきたことを指摘する。例えば、都市再開発の名のもとに、低所得者層が住む地域が取り壊され、新たな商業地区や高級住宅街が建設されるケースは世界中で見られる現象であり、これはデザインが社会的不平等を生み出す一因となっている。
第二部:デザインの存在論的再定位
第二部では、デザインを再構築するための理論的枠組みが提示される。エスコバルは、近代の二元論的思考を超え、「関係性(relationality)」を重視する視点を提唱する。ここでは、先住民の世界観やエコロジカルな知識が重要な参考になる。
例えば、ラテンアメリカの先住民社会では、「ブエン・ビビール(Buen Vivir)」という概念がある。これは、人間が自然と調和して生きることを重視する生き方であり、西洋近代的な「成長」や「発展」とは異なる価値観に基づいている。エスコバルは、こうした概念をデザインの実践に取り入れることで、より持続可能で多元的な世界を構築できると主張する。
また、この章では「ポストヒューマン的デザイン」の視点についても論じられている。従来の人間中心主義的なデザインは、環境や他の生物との関係を軽視してきたが、ポストヒューマン的視点では、人間と非人間の境界を曖昧にし、より包括的なエコロジーを考慮したデザインを模索することが求められる。
本書の意義と批評
本書の最大の貢献は、デザインを単なる技術的な手法ではなく、存在論的・政治的な行為として捉え直す視点を提示した点にある。これにより、デザインが持つ社会的・環境的影響をより深く理解することが可能になる。
エスコバルの主張は、特にデザイン分野において批判的視点を持つ研究者や実践者にとって重要な示唆を与える。しかし、その一方で、彼の理論がどのように具体的なデザイン実践へと落とし込めるのかについては、まだ議論の余地がある。特に、政治経済的な制約の中で、どのようにオルタナティブなデザインの実践が可能になるのかについては、今後のさらなる研究と実践が求められるだろう。
※ この記事はchatGPTを利用して書かれています。不正確な情報が含まれる可能性にご注意ください。